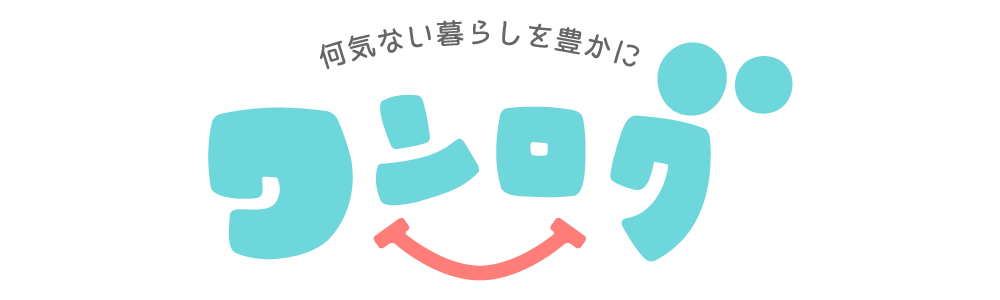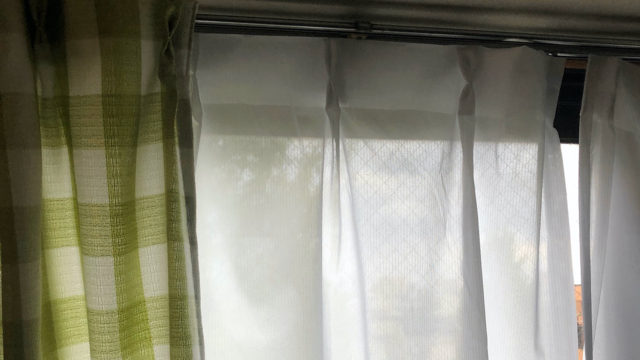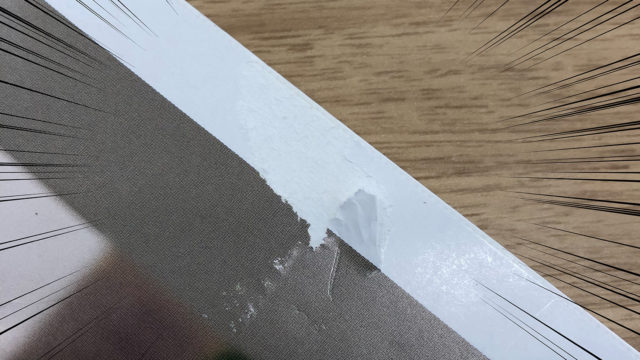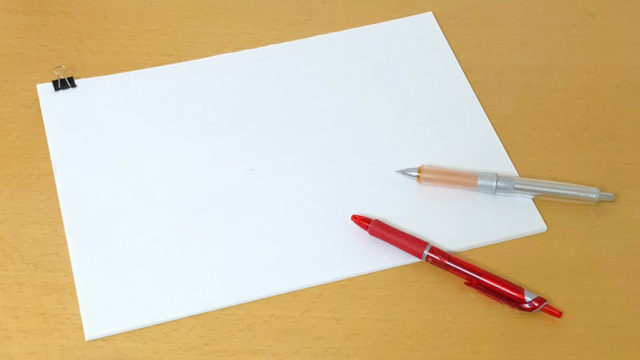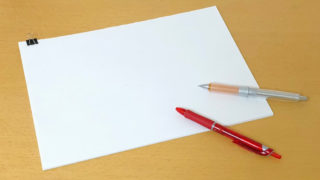美術大学を卒業して10年あまり。30代を超えてからの学生時代の友人や同級生の動向を見て、続けることの大切さを感じるようになりました。
例えば、けして美術大学時代、最も才能があって、最も華々しく活躍していたわけじゃないけれど、卒業後も愚直に創作活動を続けていた同級生が、ついに大きな公立の美術館で展覧会を開いたのを目の当たりにした時。
例えば、どちらかというと「玄人ウケ」するような作品を作って、在学中はさほど目立たなかった同じゼミ生が、今や海外やアカデミックなアート業界で活躍しているのを見聞きした時。
例えば、当初はそこまで抜群の画力があったわけでもなかった友人が、「画家になる」という目標のもと絵を描き続けた結果、今や写実画家として名を馳せている現状を目にした時。
そんな場面に遭遇する度、才能の大小というより「人はそう在り続けたものになっていくんだな」というのを実感します。

かくいう私も、美術からは少し離れた話になってしまいますが、学生時代にバイトで手伝い程度に関わっていたIT企業の仕事をきっかけに、会社を変え、サービスを変え、細い糸を辿るようにおずおずとIT系の仕事に関わり続けて今の仕事に行き着いているので、自分自身でもその原理を体感しています。
そうやって社会的な意味で物事を続けていく時に大切なのが「コンスタントに外に活動を発表していくこと」。
前述の例に挙げた同級生や友人たちも、けして毎回傑作を作っていたというわけではないけれど、定期的に、なるべく頻繁に、外に活動の成果を見せることで「そういう存在」になっていきました。
どんなに訝しげに思っていても、実際に現実として目の前に見せられると、人って有無を言わず受け入れざるを得ないんですよね。
広い意味での「社会」に向けたアウトプットを繰り返すことで、周囲の人々の、そして自分の中の「自分の在り方」を書き換えていく。その積み重ねが自分の立場を作り、それが1つの在り方として定着し結実するのに必要な時間が、10年という期間なのかなと思います。

“学校”を卒業し働き始め、30代になると、どうしても自分で生活を成り立たせねばならず、人によっては立派に家庭を築いていたりもするので、目の前のことにいっぱいいっぱいになりがちです。
目に見える結果をすぐに求めてしまって、10年も20年も先に展望を描いて、地道なアウトプットを繰り返すなんて、学生時代とは同じようにはできないことが多いでしょう。
ただ、それでも自分の中に「可能性」を感じていて、不完全燃焼の部分が残っているのなら、そこから目を逸らさず、自分の本当に在りたい「在り方」を模索することは大切なことなのだと思います。
「人はそう在り続けたものになっていく」様々な人から見て取れるその原理を念頭におくならば、自分の将来の在り方を見据え、それに向かう活動を少しずつでも積み重ねていくことは、きっとどの年齢にあっても人生の基盤を成す重要な「姿勢」の1つです。
では元気によい毎日を。